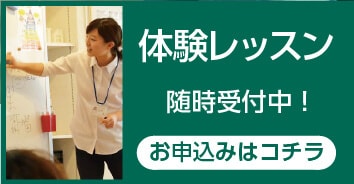
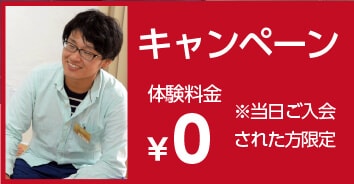

皆さんは、プレゼンテーションを成功させるために重要なことはなんだと思いますか?
事前の資料集めでしょうか、見やすいスライドを作ることでしょうか、あるいは抑揚をつけて話すことでしょうか。
すべて大事なことですよね。
しかし、何が重要なのか一言で言えば、練習を重ねることです。
上手いプレゼンをしている人たちは必ずと言っていいほど練習を怠りません。
プレゼンが成功するかどうかは練習量によって決まってくると言っても過言ではないでしょう。
この記事では「上手くなるための5つの練習法」を紹介していきます。
正しい練習方法を知っていれば効果的に上達していき、プレゼンを必ず成功に導くことができます。
プレゼンテーションの構成を一通り作り終わった後に行う、おすすめの練習方法を、5つのステップに分けて紹介していきます。
プレゼンテーションが成功するポイントは練習量が大きく関与します。一つ一つステップを踏んでいけば、あなたのプレゼンの質は向上していくはずです。
原稿を作るときは、話す内容の一語一句をすべて書き出す方法はやめましょう。
確かに、すべての内容を文書で書き出しておけば本番で何を喋ればよいか分からなくなってしまうことはなくなるでしょう。
しかし、この方法は、文章を読むことに夢中になってしまうという欠点があります。
棒読みになってしまったり、聴衆の反応に意識が向かなくなってしまい、単調なプレゼンテーションになります。
原稿を作成するときは、すべてを書き出すのではなく、話のキーワードを書き出しておくのがよいでしょう。
そのためには、キーワードを見ただけで説明ができるように、何回も練習する必要があります。
練習を積み重ねれば、もし本番で何を話せば良いか分からなかったとしても、キーワードを書いたメモを見れば次に何を話すべきか分かるようになります。

まず、よくやってしまう間違ったプレゼンの練習方法を紹介します。
パソコンの前でスライドを見つめ、頭の中で話すシミュレーションをする方法です。
この練習方法は、シミュレーションの段階ではなんとなく成功しそうなイメージが湧きます。
しかし、いざ本番を迎えると、噛んでしまう、一文が長すぎて間延びしてしまうという失敗をしてしまいます。
頭の中で考えるのみと違い、実際に話すとなると、思っていたより時間が掛かってしまったり、文字の繋がり読み辛いかったりすることがあるからです。
この失敗をしないように、プレゼンの練習をするときは、実際に声を出して読んでみましょう。
どこで詰まってしまうのか、話し辛いところはどこか、伝わりにくい箇所はどこかといった原稿の段階での失敗がよくわかります。
さらに、大まかな時間配分がわかってくるので、この段階でプレゼンとして大枠が固まってきます。
次のステップでは、自分のプレゼンしている姿を客観的に見てみましょう。
客観的に見るためにはスマホで撮影すれば動作や話し方、伝わりやすさがよく分かります。
プレゼンの練習をしている自分自身を見るのは恥ずかしさや、嫌悪感があったりして、苦痛に感じるという方もいるでしょう。
しかし、客観的な映像を見ることによって、喋り方の癖や体の動きの悪い癖といった普段無意識でやってしまっている欠点に気づくことができます。
また、話しているだけでは気づかなかった、同じような説明を繰り返してしまっている所や、間延びしてしまっている箇所といった構成の問題も聞くことで浮き彫りになります。
ここで出た問題点を修正していけば、本番でもある程度まとまった内容のプレゼンテーションができるようになります。
さらに良いプレゼンテーションにしていくために次のステップに進みましょう。

プレゼンテーションのリハーサルを見てもらい、感想をフィードバックして貰いましょう。
他の人に見て貰うメリットは2つあります。
1つ目は自分では気づかなかった癖を指摘してもらえる事です。
映像や音声で客観的に見たつもりでも、自身の悪い癖を見落としている場合もあります。
アドバイスを真摯に受けとめ、悪い所は直していきましょう。
もう1つは内容についての意見をもらえる事です。
自分では練り込んで完璧な内容に仕上げたつもりでも、他の人の視点を借りると納得のできる改善点が案外簡単に見つかるものです。
そのため、フィードバックを貰うなら上司や先輩といった発表するプレゼン内容に詳しい人に見てもらうのがベストです。
ここまで終われば、いよいよ次が最後のステップです。
最終段階として、本番と同じような環境で練習してみましょう。
同じような場所で練習することで、機材の操作方法やどのくらいの声量で話せば良いかといった本番での動きが再確認できます。
また、似た環境で練習することで、経験から精神的にも余裕が出てきます。
最近はオンラインでプレゼンテーションを行うことも多くなってきましたよね。
事前の招待方法や資料の共有方法もこの段階で練習しておきましょう。
操作に手間取り、本番中余計な時間を取られ、入念に準備したプレゼンにケチがつくのは嫌ですよね。
準備不足による不測の事態は焦りを生んでしまいます。
できる限りの前準備をすれば、本番でも自信を持って発表ができます。
紹介した5ステップをすべて実施するのはそれなりに時間が必要となります。
しかし、最後までやり切れば、練習した分が力になり必ずプレゼンテーションを成功に導いてくれるはずです。
プレゼンテーションの練習方法の5つのステップを紹介してきました。ここからは、練習をする際に気をつける話し方や、文章の構成方法のポイントを紹介していきます。
このポイントを抑えれば、伝わりやすくなるだけではなく、相手が興味を持って聞いてくれるようなプレゼンテーションに変化させることができます。
「フィラー」とは「えーっと」「あのー」「そのー」といった話の途中で出てきてしまう雑音のことをいいます。
みなさんは、フィラーが多く出てくるプレゼンテーションを聞いてどんな印象を受けるでしょうか。
自信なさげに見えたり、練習不足に感じたりとあまり良い印象は受けませんよね。
では、フィラーが出てきてしまう原因はどこにあるのでしょうか。
代表的な原因として、話す内容が頭の中で整理できていないといった、緊張や動揺といった心理的な要因によります。
プレゼンテーションの場合、喋る内容が整理できていなかったり、話す内容に自信がなかったりする箇所でフィラーがよく出てしまいます。
フィラーを無くすためには、どこでフィラーが出てしまうのかを確認しましょう。
その箇所の話す内容を自分でもう一度理解し直してから、再度練習をすれば克服していけます。

聞き取りやすい話し方として、一文を短くして、言い切るという方法があります。
まずは悪い例を見てみましょう。
×「よくある管理職の愚痴として、部下が相談に来ないという悩みがありますが、この問題は実は上司の方に原因があるという面白い研究結果が、最近発表されたので、今日は取り上げて行きたいと思います。」
次に良い例を見てみましょう。
○「よくある管理職の愚痴として、部下が相談に来ないという悩みがあります。
この問題は、実は、上司の方に問題があるという研究結果が最近発表されました。
面白い内容なので今日取り上げて行きたいと思います。」
実際に声に出して読んで貰うとよく分かりますが、悪い例は読んでいて疲れてしまいまよね。
聞いている方も同じで、一文が長いと頭に入って来にくくなってしまいます。
一文を短く区切ると、聞きやすいだけではなく、アクセントも付けることができ、惹きつける話し方をすることができます。
自分のプレゼン練習を聞いている段階で、一文が長くなっていないか注意して、短い文で話すようにしましょう。
改善していくと単調なプレゼンから、聞いていて興味が湧いてくるプレゼンに変化していくでしょう。
自分が伝えたい内容がスムーズに伝える方法として、prep法という話し方があります。
prep法とは
Point(主張)
Reason(理由)
Example(具体例)
Point(主張)
の順番で話す話の手法のことを言います。
例をだしてみましょう。
プレゼンテーションにおいて一番大切なことは練習を重ねることです。(Point)
なぜなら、相手に伝わりやすい話をするためには様々な自分の悪い癖を矯正しなければならないからです。(Reason)
例えば、「えーっと」「あのー」「そのー」といった言葉を途中で挟み過ぎてしまうと聞き手の集中力は落ちてしまいます。(Example)
聞き取りやすい話し方をして、プレゼンテーションを成功させるために練習を怠らないようにしましょう(Point)
この方法で話すと、初めに主張があるので何を伝えたいのかが相手に分かりやすくなります。
その上で理由や具体例を出し説得力をだし、最後に再び主張をすることで、伝えたい事を印象付けることができます。
プレゼンテーションのような相手に特定のことをアピールするような場面ではうってつけの手法と言えるでしょう。
プレゼンテーションをする上で、聞き手にどれだけ興味を持って貰えるかということ重要になってきます。
聴衆の体験とプレゼンでの話をリンクさせるために、分かりやすい例え話を入れるようにしましょう。
例えば、年配の人向けにプレゼンテーションをするときに、自分たちの世代が子供の頃に体験した例え話をしたとしても、あまり共感をして貰えないですよね。
プレゼンテーションの聞き手は誰なのかを想定しつつ、その人たちに向けた分かりやすい例え話を入れていくと、伝えたいことが伝わるようになるでしょう。
プレゼンテーションが上手くなるもう一つのコツとして普段の会話から、自分の弱点を鍛えていくという方法もあります。
例えば、声が小さい、トーンが低い、分かりやすい例え話し方ができない、といった弱点があるのであれば、普段の話し方から改善するように意識していけば克服できます。
それだけではなく、練習したプレゼンテーションで行っているような話し方がミーティングや後輩を指導する場でも出来たらどうでしょうか。
仕事にもきっと良い影響がでてきますよね。
紹介した話し方のポイントはプレゼンテーションに限った話だけではなく、普段の仕事でも役に立つことが多くあります。
プレゼンテーションの成功ために、普段の話し方を変えていくと仕事でも成果が出てくるようになります。
日常での会話方法から変えて、伝わりやすい話し方をしていくようにしてみてください。
プレゼンテーションの練習方法を5つのステップに分けて紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
練習方法は理解したけど、緊張をしてしまいプレゼンテーションが上手くいかなかった経験から不安があるという方もいるのではないでしょうか。
そんな方はコミュニケーション講座に通ってみるのも一つの手です。
アトリエシャンティのコミュニケーション講座では、プレゼンテーションに必要な人前に出ても緊張しない練習や、相手が知りたいことは何かを読み取るトレーニングといった社会人の方にも役に立つレッスンも行っています。
プレゼンテーションの練習をしたいけど、協力をたのめる先輩や同僚、友人がいないという問題を抱えている方もいると思います。
そんな悩みもアトリエシャンティのコミュニケーション講座ならば解決できます。
なぜなら、入会者一人一人に専属の講師がつくからです。
マンツーマンでレッスンを行う機会もあるので、プレゼンテーションを講師に見てもらいフィードバックやアドバイスをして貰うといったことも可能です。
岐阜・名古屋・富山・石川で体験レッスンを開催中です。
会員さん一人ひとりを大切にするために、会員数を限定させていただいています。
気になる方はお早めにお申し込みください!
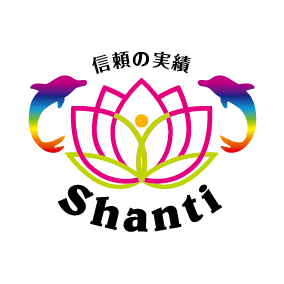
コメント